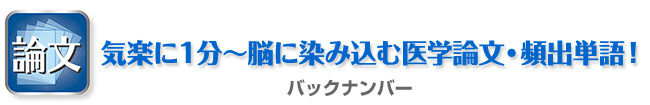
2013年5月まで配信していたメールマガジン『気楽に1分~脳に染み込む医学論文・頻出単語!』の全バックナンバーを公開します。
主要医学ジャーナル4誌(N Engl J Med,JAMA,BMJ,Lancet)に掲載された100論文の全単語から,英文の“核”とも言える動詞だけを集めて使用頻度を解析。このうちランキング上位の動詞を,ランダムに取り上げています。
バイリンガルの富田氏が語る「単語の持っているイメージ,ネイティブが感じるニュアンス」は,まさに“目からウロコ”の感涙もの!
1つの動詞を3つの違った角度から学習できるので,その使い方が徐々に脳に染み込みます。
月~金曜にわたり,毎日1単語ずつ,全100単語分のバックナンバーを順次公開していきます。お楽しみに!!
No. 66
represent
意味:表す,相当する
単語のイメージ:ある事象と同等である,ある事象に成り代わる
例文
(1)Smoking represents a risk factor for developing social anxiety disorder.
(2)According to humoral doctrine in ancient times, four humors, "Blood", "Yellow bile", "Black bile" and "Phlegm" represent four types of temperaments.
単語チェック
- risk factor 危険因子
- developing 発症する
- social anxiety disorder 社会不安障害
- humoral doctrine 体液説
- ancient times 古代
- humors 体液
- Yellow bile 黄色胆汁
- Black bile 黒色胆汁
- Phlegm 粘液
- temperaments 気質
対訳
(1)喫煙は社会不安障害を起こす危険因子である。
(2)古代の体液説によると,4つの体液とされる「血液」「黄色胆汁」「黒色胆汁」「粘液」は4種類の気質を表している。
ミニ解説
(1)は日本語だけを読むと,is を使って “Smoking is a risk factor…” と英訳してしまいそうですが,is と represent ではニュアンスに大きな違いがあります。is を使うと「喫煙=危険因子」の意味になりますが,represent を使うと,単に「喫煙=危険因子」ではなく,「その背景にあるさまざまな事象をひっくるめた危険因子」といったニュアンスが出てきます。したがって,今回の例文では,社会不安障害という精神障害の危険因子として,喫煙という行為だけではなく,喫煙行動に至るまでの心理的な動きのあることが示唆される represent のほうが適しているわけです。
逆に,これを肺がんのような身体的変化の危険因子として論じたい場合は,肺がんと喫煙を直接結びつけることができるので,is が適当です。
この違いを,次の2つの文章で比べてみましょう。
《例文》
A. Smoking is bad for your health.
(喫煙は健康を害する)
B. Smoking represents bad health.
(喫煙は不健康であることを表す)
B は,煙草を吸うということは,何らかの精神的な問題を抱えた不健康な状態であるかのような表現です。B を A と同じ意味になるように represent を使うとすると,次のようにする必要があります。
《例文》
Smoking represents one of the risk factors to your health.
(喫煙は健康を害する危険因子の一つである)
これをもう少し簡単にしようとして,Smoking represents risk factors to your health. とすると,「喫煙は健康を害する危険因子の代表である」という意味になってしまいます。
問題
(1)この値はベースラインから約3倍の増加に相当する。
(2)(この)図の赤い点線は,治療を受けた患者を示している。
ヒント
※(2)の「(この)図の」は in this figure で表現しましょう。
- 3倍の増加 a three-fold increase
- 点線 dashed line
解答例
(1)This value represents almost a three-fold increase from baseline.
(2)The red dashed line in this figure represents treated patients.
ミニ解説
(2)は,以下のように受動態でも表現することができます。
《例文》
In this figure, treated patients are represented by the red dashed line.
このような受動態は能動態に比べてもったいを付けた言い方と捉えられますから,論文向きとも言えるかもしれません。ただ,ネイティブは基本的に受動態よりも能動態を好んで使います。そのほうが文章がコンパクトになり,「誰が/何が」「何をしたか」が明快で,余計な誤解を招かないからです。受動態を使うと文章が長くなり,読み手にとって分かりづらくなることがありますから,特に話が複雑なときは,たとえ論文であっても,能動態で表現できるものはできるだけ受動態を使わないようにするのが賢明です。英語で文章を作るときは,まず動詞を決め,次にその動詞が能動態で使えるものを主語にすると,意味の間違いが起こりません。
例文
(Q)What does the steep reduction represent?
(A)It shows that a strong stimulation was transmitted to a neuron.
単語チェック
- steep reduction 急激な低下
- stimulation 刺激
- was transmitted to ~に伝えられる,伝わる
- neuron 神経細胞,ニューロン
対訳
(Q)数値の急激な低下は何を表していますか。
(A)強い刺激が神経細胞に伝わったことを示しています。
ミニ解説
今回の会話例の(Q)では,the steep reduction と冠詞 the が使われていることから,会話をしている2人の前に何か特定のデータがあることが伺えます。
これに対し,a steep reduction と冠詞 a を使うと,It shows ... という(A)の答えは成り立ちません。この場合,特定のデータについて聞くのではなく,「(数値の)急激な低下 ‘とは’ 何を指すのですか」という意味になり,返答は次のようになります。
《例文》
In this case, it will represent the times that a strong stimulation was transmitted to a neuron.
(このケースでは,強い刺激が神経細胞に伝わった時を指すことになります)
冠詞は日本語に存在しないため,その使い方に苦労している人も多いと思います。小さな単語なのに,大きな意味の違いを生むこともある実に厄介な存在です。文章を書くときに a を使うか,the を使うか,複数形にするか,冠詞を付けないかなど,規則を覚えることも大事ですが,さまざまなネイティブの文章を読み,少しずつ感覚を身につけていくのが,結局近道なのかもしれません。


