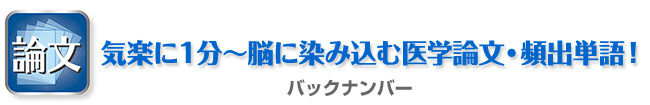
2013年5月まで配信していたメールマガジン『気楽に1分~脳に染み込む医学論文・頻出単語!』の全バックナンバーを公開します。
主要医学ジャーナル4誌(N Engl J Med,JAMA,BMJ,Lancet)に掲載された100論文の全単語から,英文の“核”とも言える動詞だけを集めて使用頻度を解析。このうちランキング上位の動詞を,ランダムに取り上げています。
バイリンガルの富田氏が語る「単語の持っているイメージ,ネイティブが感じるニュアンス」は,まさに“目からウロコ”の感涙もの!
1つの動詞を3つの違った角度から学習できるので,その使い方が徐々に脳に染み込みます。
月~金曜にわたり,毎日1単語ずつ,全100単語分のバックナンバーを順次公開していきます。お楽しみに!!
No. 57
increase
意味:上昇させる,上昇する,増加する,増加させる
単語のイメージ:球体が膨らむように3次元で増えるのではなく,下から上へと2次元で増えていく感じ
例文
(1)The risk of cardiovascular death increased 3-fold in arm A compared with arm B.
(2)Bisphosphonates are prescribed to increase bone mineral density of the osteoporosis patients.
単語チェック
- cardiovascular death 心血管死
- 3-fold 3倍
- arm 群
- Bisphosphonates ビスホスホネート製剤(骨粗鬆症の治療薬。破骨細胞による骨吸収を抑える)
- are prescribed 処方される
- bone mineral density 骨密度
- osteoporosis 骨粗鬆症
対訳
(1)A群はB群と比べ,心血管死のリスクが3倍に増加した。
(2)ビスホスホネート製剤は骨粗鬆症患者の骨密度を増やすために処方される。
ミニ解説
「増える」や「多くなる」にはたくさんの表現法がありますが,上下するものや計測できるものには increase が使われます。(2)の密度も「決まった枠の中で“ある物”が増えていく」わけ
ですから increase になります。これが,例えば「“ある物”が増えることで全体が膨らんでいく」のであれば,「ある物」が increase した後,全体が expand するといった言い方になります。
また,increase とよく似た意味を持つ動詞に elevate があります。elevate の意味は「(~のレベルまで)高める,上昇させる」です。同じ「上昇させる」でも,elevate では「高いところまで」というニュアンスが出てきます。
《例文》
If your blood pressure was 115/70 and it increased to 120/80, that would not be elevated blood pressure, but it certainly is increased from baseline.
(血圧が115/70の人が120/80になった場合,高血圧ではないが,明らかにベースラインよりは上昇している)
問題
(1)そのデータから,低酸素状態がXXの産生を増加させることが明らかになった。
(2)カルシウムの吸収は用量依存的に増加した。
ヒント
※(1)は The data demonstrated that の形を使いましょう。
- 低酸素の hypoxic
- 吸収 absorption
- 用量依存的に dose-dependently
解答例
(1)The data demonstrated that hypoxic conditions increased the production of XX.
(2)Calcium absorption increased dose-dependently.
ミニ解説
ここでは,(1)の condition が複数形になる点に注目しましょう。ただ単に「低酸素状態」というと分かりにくいですが,「低酸素な状態のとき」と考えるとどうでしょうか。そのような「状態になる回数」があることが分かりますね。回数があるのですから,数えられます。したがって,もし(1)の hypoxic condition が単数であったなら,低酸素状態はモニター期間中に1度だけ起こった,ということになるわけです。
論文では,事象をきちんと整理しなくてはならないので,数えられる単語の場合,単数か複数かで,その事象が1回なのか複数なのかが明確になりますが,会話ではそうでもありません。特に米国人の場合は,口癖のように複数形を使うことが多いようです。このため,文章中でも時折誤って s が付いていることがあり,英語論文のチェッカーが悩まされるところです。図や表は,こういった小さな誤りを見つけることに思いのほか役立っているそうです。
例文
(Q)Which of the laboratory values was increased by treatment with drug A?
(A)The levels of HDL cholesterol increased, as we expected.
単語チェック
- laboratory values 検査値
対訳
(Q)A薬による治療で,どの検査値が上昇しましたか。
(A)予想通り,HDLコレステロールの値が上昇しました。
ミニ解説
英語にも能動態と受動態がありますから,動詞を能動的に使えるものを主語にするだけでなく,当然,受動的に使えるものを主語にすることもあります。今回の会話例ではその両方を使っています。これは動詞の使い方を優先した考え方ではなく,主語が何かを優先的に考えた文章の作り方で,その違いが出たよい例です。
(Q)は,どの検査値が「上昇させられたか」を問いたいので受動態を使い,(A)は,この検査値が「上昇した」と言いたいので能動態で答えたわけです。(Q)の主題は「検査値の変化」ですから,「A薬によって何が起こったか」を問う聞き方ですね。これは What was increased ~ と聞いてもよく,答えは What を明らかにする単語を主語にして,HDL cholesterol increased ~ と能動態になります。


